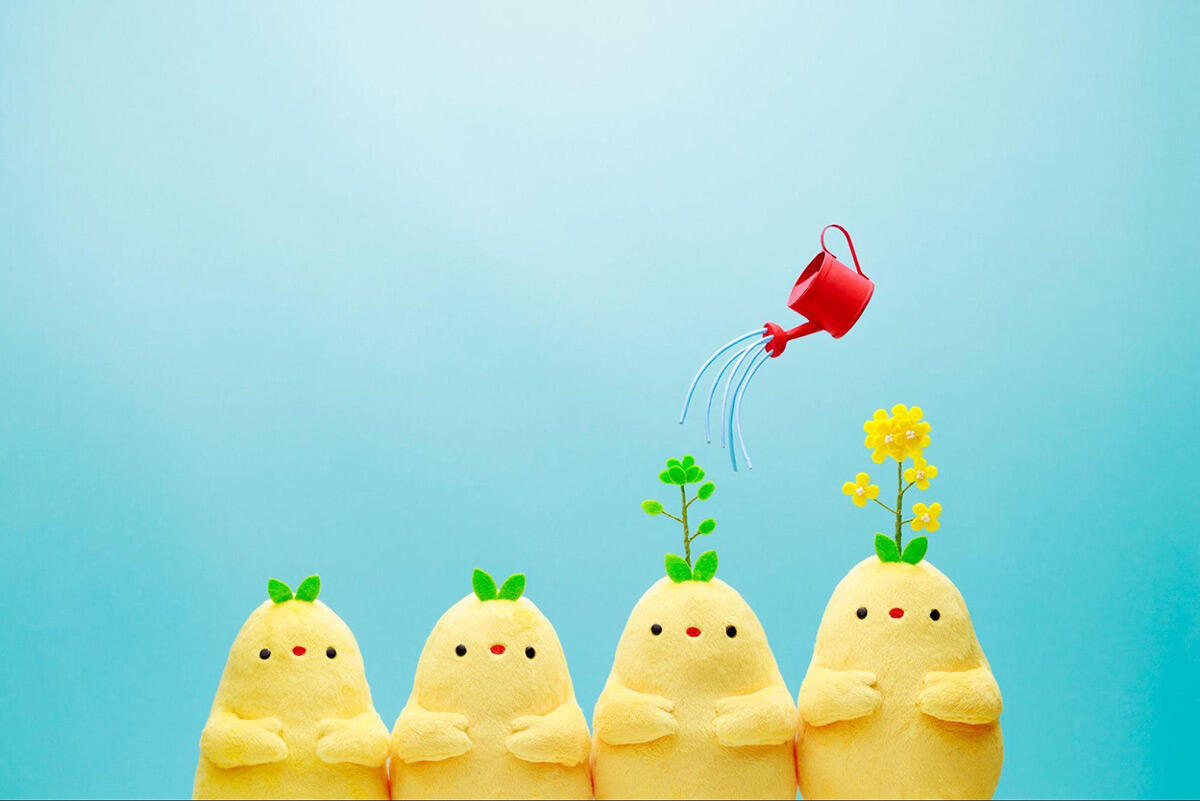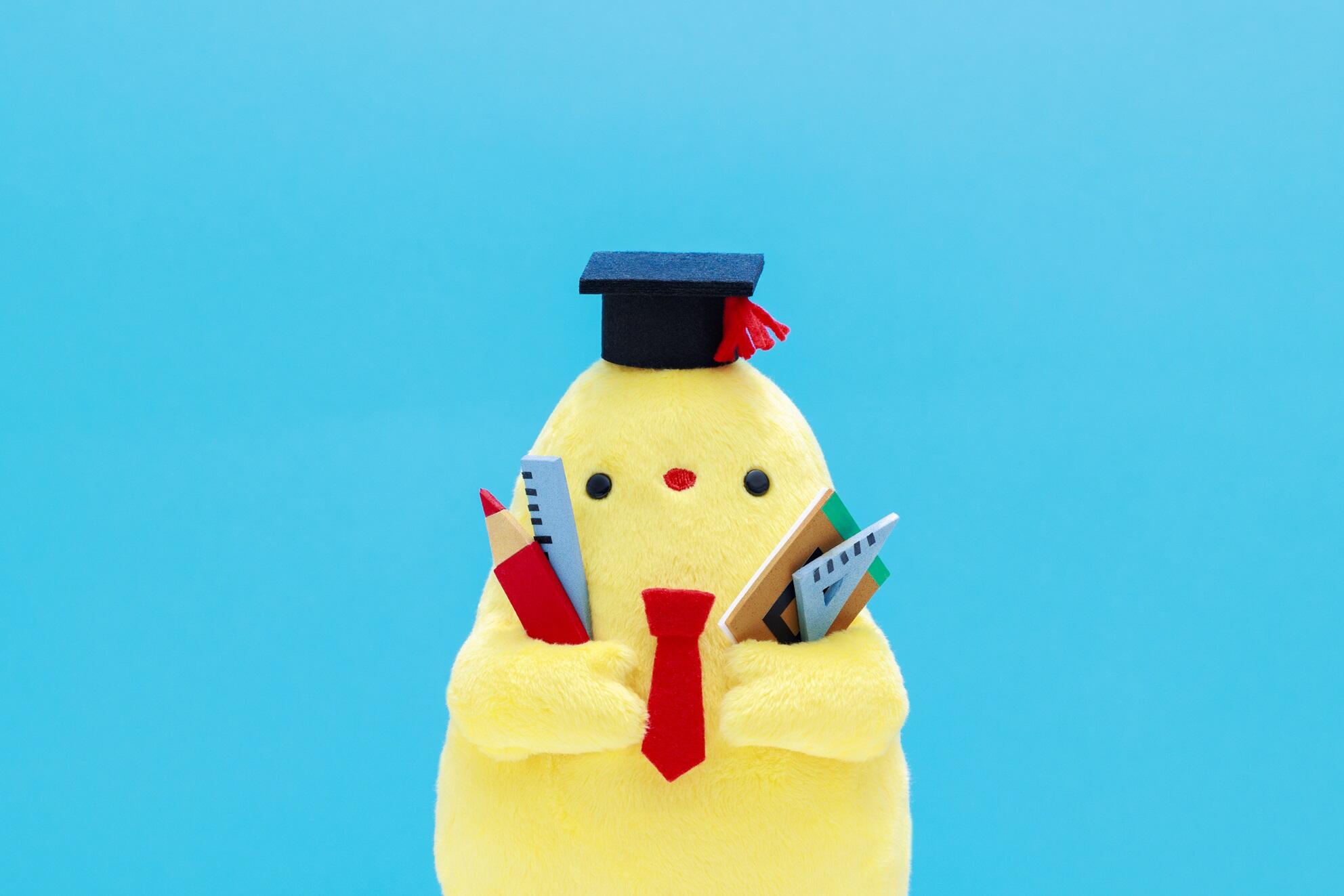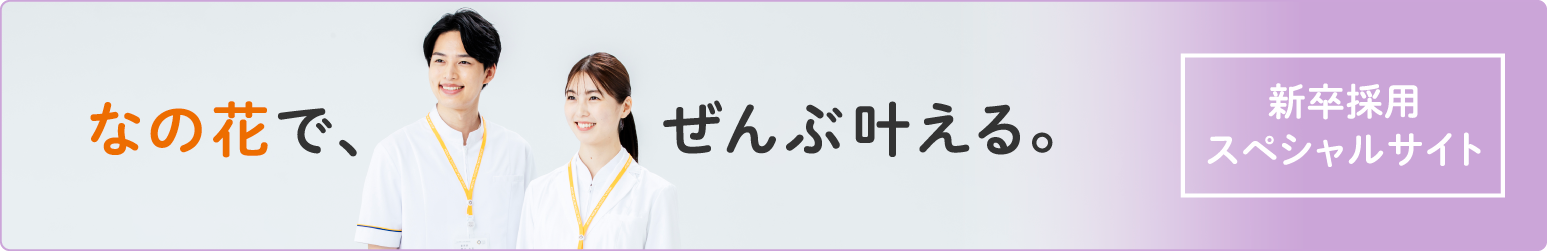2025.01.30
薬剤師の知識
調剤ミス防止のためにやるべき工夫や対策を紹介!ミスの原因も
目次
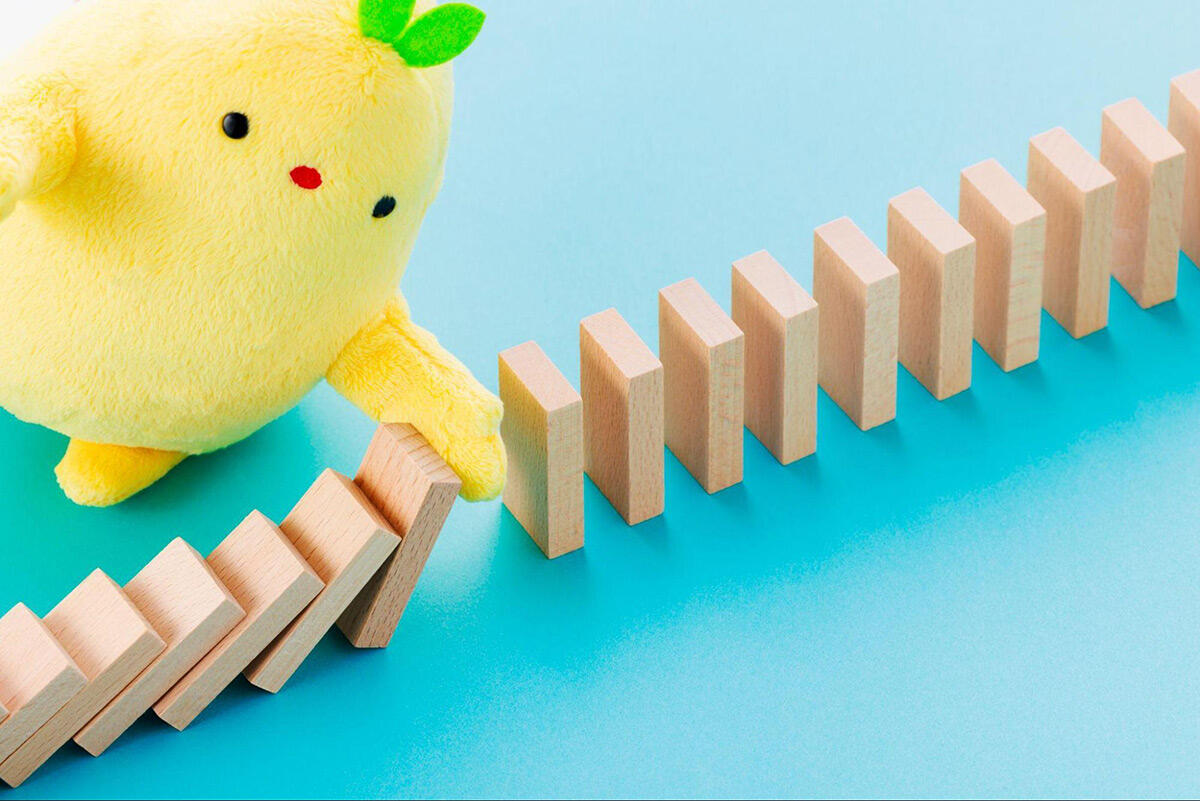
こんにちは!なの花薬局の森本です。
調剤は、正確性が何より大切です。
調剤ミスは、患者さまに健康被害を引き起こす恐れがあるためです。
実際に、過去には調剤ミスにより薬剤を服用した患者さまが亡くなり、薬剤師が刑事責任を問われる事件も発生しています。
では、調剤ミスを防ぐには、薬剤師はどのような対策を取れば良いのでしょうか。
今回は、調剤ミスを防止するために効果的な工夫を、ミスの原因とともにご紹介します。
調剤ミスとは?
調剤ミスとは、薬剤師が行う調剤作業のミスのことです。
日本薬剤師会では、調剤ミスを以下の3種類に分類し、定義しています。
1.調剤事故
2.調剤過誤
3.インシデント事例
まずは、これらの定義について確認していきましょう。
調剤事故
調剤事故とは、調剤行為に関わる事故のうち、薬剤師の過失の有無に関わらず、患者さまに健康被害が発生しているものを指します。
医療事故の一種であり、「アクシデント事例」と呼ばれることもあります。
調剤過誤
調剤過誤とは、前述の調剤事故のうち、薬剤師の過失によって発生したものを指します。
具体的には、調剤の間違いはもちろん、患者さまへの服薬指導の間違いや説明不足による健康被害の発生が調剤過誤と判断されます。
インシデント事例
インシデント事例とは、患者さまに健康被害は出なかったものの、"ヒヤリ"や"ハッ"とするようなミスを指します。
「ヒヤリ・ハット事例」とも呼ばれます。
健康被害が発生していないミスについては、薬剤の交付前か後か、患者さまの服用前か後かは問わず、インシデント事例に分類されます。
調剤ミスを防ぐにはミスの原因を知ることも大切
調剤ミスを防ぐには、まずミスの原因を知り、それを解消することが大切です。
調剤ミスの代表的な原因は、次の4つの問題に分けられると考えられます。
- 人的問題
- 組織体制の問題
- 連携上の問題
- 物・表示に関する問題
各原因について詳しくみていきましょう。
人的問題
調剤ミスの原因としてまず考えられるのは、人的問題(ヒューマンエラー)です。
調剤業務では、処方箋の読み取りや服薬に関する情報の確認、必要に応じた医師への疑義照会など、指示された薬剤を調剤するまでの一連の作業が求められます。
この複雑な作業を正確にこなすためには、高い集中力と体力が必要です。
しかし、薬剤師が疲労や寝不足、ストレスなどの身体的・心理的な問題を抱えている場合、調剤作業におけるミスのリスクが高まる可能性があります。
また、薬剤師自身の知識不足もミスの原因になります。
医療・医薬品は日々進歩しているため、薬剤師は常に知識をアップデートしていなければなりません。
古い知識で対応することで、調剤ミスが発生してしまう可能性があります。
さらに、作業に対する慣れも、ミスにつながる原因の一つ。
慣れによる慢心で注意を怠ったり、確認を省略したり、マニュアルに違反したりした薬剤師がミスを起こす例は少なくありません。
組織体制の問題
組織の体制が原因で調剤ミスが起こるケースもあります。
例えば、人材不足が深刻で一人ひとりの業務量が過剰になっている場合や、現場のフォロー体制が十分に整備されていない場合、ミスのリスクが高まります。
また、薬剤師の教育制度が不十分であることもミスにつながる要因の一つです。
研修制度や業務マニュアル、新人のサポート体制などがしっかり整備されていない場合、薬剤師のスキルが標準化されません。
このような環境では、スキルの向上が難しくなり、結果としてミスが増える可能性が高まります。
連携上の問題
薬剤師が業務を進める上で、同僚の薬剤師や医師との連携は欠かせません。
しかし、この連携が十分に取れない場合、調剤ミスの原因となることがあります。
例えば、他の薬剤師と引き継ぎが不十分であったり、医師への疑義照会をためらうような状況が生じたりする場合、ミスのリスクが高くなるでしょう。
また、薬剤師が患者さまとしっかりコミュニケーションを取れていないことも、アクシデントまたはインシデントにつながる可能性があります。
物・表示に関する問題
調剤ミスは、物や表示に関する問題によって発生することもあります。
例えば、異なる薬剤のパッケージが似ていたり、調剤室が整理整頓されていなかったりする場合、薬の取り違えなどのミスが起こりやすくなります。
さらに、調剤に使用する機械の操作が分かりにくいと、誤った使い方によってミスが発生する可能性もあります。
調剤ミスを防止するためにできる工夫とは?
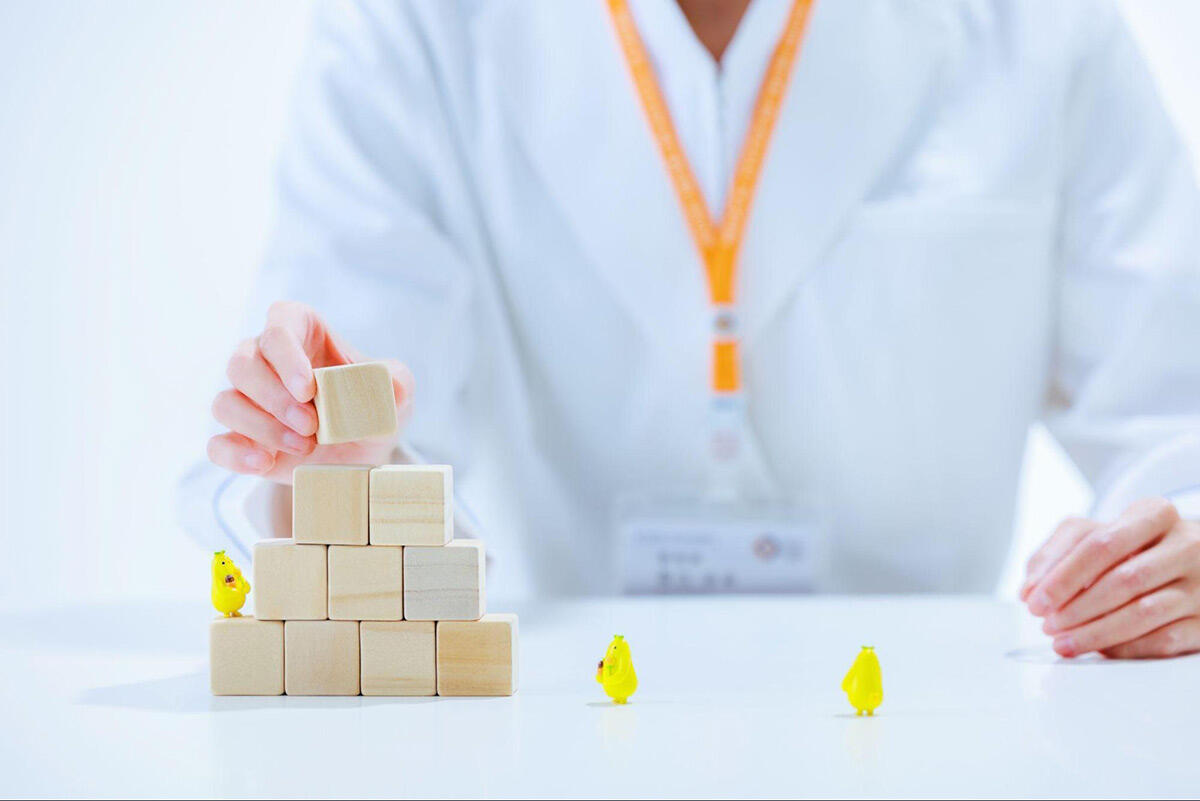
ここからは、調剤ミスを防ぐための工夫についてご紹介していきます。
調剤ミス防止に効果的な6つの工夫
以下のような工夫は、調剤ミス防止に効果的です。
- 整理整頓を徹底する
- 確認・調査を怠らない
- ダブルチェックを行う
- パッと見てわかる工夫を行う
- 自動化システムを導入する
- 起こったミスは原因検証を行い報告する
6つの工夫について詳しくご説明します。
整理整頓を徹底する
調剤室の整理整頓ができていないと、薬の取り違えが起こりやすくなり、調剤ミスのリスクが高まってしまいます。
ミスを防ぐためには、「どこに何があるか」が一目でわかる環境をつくることが大切。
これは、業務の効率化にも有効です。
調剤室だけでなく、患者さまが過ごす待合室も常に整った状態を保つよう心がけましょう。
日頃から環境を整えることで、より安全で効率的な業務が実現します。
確認・調査を怠らない
正確な調剤のためには、確認と調査を怠らないことが大切です。
作業は何度も確認しながら慎重に進め、わからないことはそのままにせず、疑義照会などを通してすぐに調べるようにしましょう。
ヒューマンエラーを防ぐためには、声に出して確認したり、指差し確認を取り入れたりすることも効果的です。
ダブルチェックを行う
1人の薬剤師が行なった調剤を他の薬剤師が確認するダブルチェックは、ミスの防止に効果的です。
ダブルチェックを通して、薬剤師同士が互いに助け合う意識を持つことも期待できます。
また、処方箋や処方薬を患者さまと一緒に確認することも重要な業務です。
この業務は、ミスを未然に防ぐだけでなく、患者さまが薬について理解を深める助けにもなります。
丁寧な説明と確認を心がけることで、より安全で信頼性の高い医療を提供できます。
パッと見てわかる工夫を行う
薬剤師は、毎日膨大な種類の医薬品を扱い、多くの調剤を行います。
そのような中でミスなく作業を進めるためには、物の置き方や表示について視覚的な工夫を行うことが大切。
例えば、患者さま・施設ごとにトレイを色分けする、クリップで目印をつける、薬袋に通し番号を振る、間違えやすい薬は離して配置する、操作のマニュアルを機械に貼っておくなどの方法が考えられます。
ちょっとした表示や物の置き方の工夫でミスのリスクを低減できます。
自動化システムを導入する
ヒューマンエラーのリスク低減策として、自動化システムを導入することも検討しましょう。
具体的には、調剤ロボットやハンディシステムの導入が考えられます。
ただし、システムを使いこなすには正しい知識が必要になります。
調剤業務の自動化は、AIの活用によって、より発展していく可能性があります。
「薬剤師の業務はAI活用でどう変わる?未来の医療を考えよう」も参考にしてください。
起こったミスは原因検証を行い報告する
ミスが起こったときには、必ず原因の検証を行い、再発防止策を作成するようにしましょう。
原因検証・再発防止策の作成を重ねていくことで、ミスが起こりにくい環境を作ることができます。
また、ミスの発生については、薬局内で共有するとともに、薬剤師会などの機関にも報告するようにしましょう。
情報を広く共有していくことは、医療安全の向上につながります。
なの花薬局の調剤ミスを防ぐための工夫
なの花薬局でも、調剤ミスを防ぐためのさまざまな工夫を行なっています。
処方箋の内容と薬歴の確認を徹底し、疑義照会も積極的に行うとともに、患者さまにも体質や体調などについて詳しくお聞きしています。
アレルギーの有無や副作用歴、併用薬、既往歴等を確認するために「質問表」をご記入いただくのも、調剤ミスを防ぐための工夫の一つです。
バーコードとハンディシステムを活用したお薬の照合や、2人の薬剤師によるダブルチェック、処方後の薬歴の管理なども実施。
患者さまにも丁寧に服薬指導・説明を行い、処方後の電話でのフォローも実施しております。
これらの取り組みによって、患者さまに安心して薬をお受け取りいただける環境づくりを進めています。
調剤ミス防止のためには原因の理解と工夫が重要!
調剤ミスは、調剤事故・調剤過誤・インシデント事例の3つに分けられ定義されています。
これらのミスの発生を防ぐためには、その原因を知り、原因に合わせて工夫を行うことが大切です。
調剤ミスの主な原因は、人的問題や組織体制の問題、連携上の問題、物・表示に関する問題にあります。
これらの原因によるミスは、整理整頓や確認・調査の徹底、ダブルチェックの実施、視覚的工夫、自動化システムの導入などによって軽減できます。
万が一ミスが起こった場合には、原因の検証や再発防止策の検討を行い、薬局や業界内で情報を共有するようにしましょう。
なの花薬局でも、調剤ミスを防止するためにさまざまな対策を行なっております。
なの花薬局では、薬剤師の就活に役立つ情報を随時発信しています。
薬剤師を目指す方、また薬剤師の働き方について知りたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね!